|
2024年の原油相場で注目された材料やイベントを振り返り、25年相場をどう見るか、7人の金融機関やシンクタンクのアナリスト、さらに独立系アナリストなど多様な専門家に見通しを聞いた。
24年の原油相場について、複数のアナリストから「中東情勢を巡る地政学リスクが最も大きなテーマだった」との声が寄せられた。一方、「総じて上値は限定的だった」との見方も複数示された。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの芥田知至主任研究員は、米中の景気減速観測などから上期は上値が抑えられたとし、米国景気は思いのほか底堅さを示したものの、「中国景気は停滞感が想定よりも強まり、石油需給は緩和気味で相場は弱含みで推移した」と振り返った。
また、エネルギー・金属鉱物資源機構の野神隆之首席エコノミストもウクライナとロシアの紛争、中東情勢の不安定化等の要因があった割には「明確な上昇傾向を示すことなく比較的落ち着いていた」とまとめ、想定よりも上値が限定的だったとした。
なお、中国の経済減速、とくに石油需要の鈍化、中国政府などによる景気刺激策に対する市場の失望に加え、一部OPECプラスの産油国が実施している日量約220万バレル程度の自主的な追加減産が25年に延長されない、もしくは拡大しないどころか、段階的縮小に動いたのは意外な材料だったとした。
24年の原油相場は方向感が欠如していた意見も散見された。ニッセイ基礎研究所の上野剛士上席エコノミストは、地政学リスクは情勢が極めて流動的で予見可能性が低いため、「先行きの展開が見通しづらい一年だった。上昇と下落リスクが共に顕在化したため、結果的に価格が予想の範囲に収まった」とまとめた。同氏によると、年初の段階ではWTI原油を1バレル60ドル弱~90ドルと予想。下落要因を中国需要の予想以上の低迷、上昇要因をイランとイスラエルの武力衝突など、想定外に中東情勢が緊迫化したことを挙げた。
さらに「通年で明確なトレンド形成ができなかった。特に下期は『需給要因の売り』と『地政学リスクの買い』を短いタイムスパンで繰り返し続けた1年だった」と語るのは、マーケットエッジの小菅努代表取締役だ。「24年は23年の取引レンジ内で推移。年間の値幅は19年以来の狭いレンジを形成」という。OPECプラスの減産政策が強化されたものの、出口戦略がみえず、構造的な需給変化に際して需給管理を行うことの難しさが印象付けられたと指摘する。「地政学リスク起因の大規模供給障害は発生しなかったが、あくまでも結果論であり、イスラエルとイランの軍事衝突などはリスク評価が難しかった」と分析した。
野村證券の高島雄貴エコノミストは、4月にみられたイランとイスラエルの直接的な応酬、それらに伴う原油価格の大幅上昇は想定外だったとし、「供給過剰を背景とした下落基調は見通しに沿ったものとなった」と振り返る。一方でOPECプラスが自主減産の規模縮小に舵を切ったため、原油価格が弱含むなか、「OPECプラスによる協調減産継続の困難さが改めて示唆されたと考えている」とまとめた。
なお、中国景気懸念を主な背景として石油の供給過剰が注目され、相場が下落基調になる見通しには合致したと述べた。
楽天証券経済研究所の吉田哲コモディティアナリストは、この数年間続くレンジの上限を作る下落圧力と下限を作る上昇圧力に挟まれ続けたとし、「高値こそ23年の90ドル台に届かなかったが、22年末ごろから続いている80ドルを挟んだプラスマイナス15ドル程度のレンジ内に収まった」と語る。上昇圧力は、OPECプラスの減産や産油国の紛争など「主要産油国からの供給減少観測」、そして資金調達を円滑にして景気回復機運を高めることで「米国の利下げ方針への転換や利下げ進展観測」などを挙げた。
一方、大手不動産企業の不振や沿岸部の若者失業率上昇、地方自治体の債務増などに苦しむ「中国の景気減速懸念」などが相場を圧迫させたと分析した。
なお、総括として「全体的に24年はこれまで以上に材料を点で見てはならない、複数材料を線で、さらに線で面を描く必要があった」とまとめた。
マーケットリスク・アドバイザリーの新村直弘共同代表は、地政学動向が価格を左右したと触れつつ、「それ以上に米国景気見通しが不安定で金融政策の動向も想定外となることも多かった」とし、ラニーニャ現象発生が遅れたものの、「ハリケーンの発生が増えやすいエルニーニョ現象の影響が長期化したことも想定と異なった」と述べた。
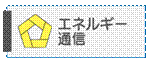
|